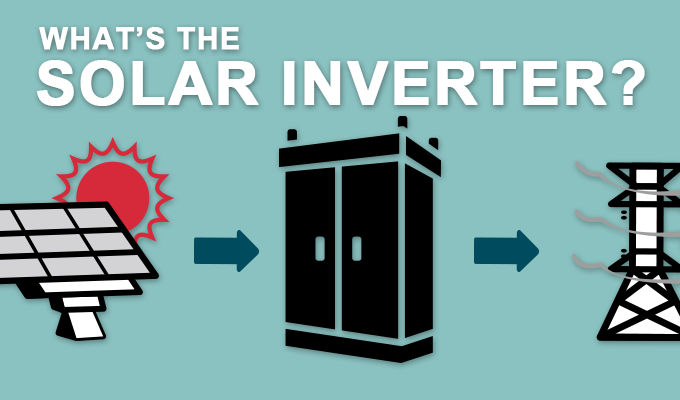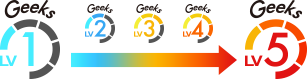発電量を最大化!パワーコンディショナのメンテナンスについて


- パワーコンディショナは計画的なメンテナンスで、長期間安定的に運営できる。
- 日常点検では目視で異常の有無を確認する。
- 定期点検ではメーカーが感電や漏電の危険性を予防する絶縁抵抗測定を実施する。
- メンテナンスの頻度は規定されていないが、要因を考慮して頻度を決める必要がある。
太陽光発電システムで作った直流電力を、家庭やビルでも使用できる交流電力に変換するためのパワーコンディショナ。長期間安全に運用するためにも定期的なメンテナンスを行うことが重要です。ここでは、パワーコンディショナのメンテナンス方法や頻度について紹介いたします。
1.パワーコンディショナには計画的なメンテナンスが必要
パワーコンディショナで使用される部品には、電解コンデンサ、換気フィルタ、冷却用ファンなど経年劣化する部品もあります。定期的なメンテナンスを行うことで、太陽光発電を長期間に渡り安定的に運用することができ、さらに発電量を最大限に引き出すことにもつながります。
主なメンテナンスの目的・メリット
- ●外面の破損や腐食、通気口の目詰まり、劣化部品などを早期発見できる。
- ●機器の保全費用や発電機会の損失を抑えることができる。
- ●定期的なメンテナンスによりトータルの維持費を安く抑えることができる。
2.パワーコンディショナの日常点検
目視等により実施する点検を「日常点検」といいます。
フィルタの清掃や交換、錆などの補修、目視による異常確認などを計画的に行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。一般的に、日常点検では以下の表にある内容を確認します。
| 点検項目 | 点検事項 | 点検方法(概略) | 処置方法 |
| 周囲環境 | 周囲温度、 湿度、 塵埃の有無 |
装置周囲の温度、湿度が 使用範囲内であることを、 温湿度計により確認 |
故障の原因になるため、 使用範囲に入るよう 周囲環境を整える |
| 外観 | 外箱のサビ等の腐食 | 装置の外観に、サビ等の 腐食が発生していないか 目視により確認する |
サビ等の腐食はサビを 落としたうえで 補修用塗料で補修する |
| 内部 | 異常振動、 異常音、 異臭の有無 |
正常時と比べ、大きな振動、 異常音、異臭等がないか確認 |
異常があればメーカーに 連絡する |
| 外部配線の損傷、 接続端子の緩み |
外部配線に損傷がないこと、 接続端子に緩みがないことを 目視により確認 |
損傷が認められた場合、 施工会社に連絡する |
|
| 扉換気ファン | 異常振動・ 異常音の 有無 |
・回転していることを目視に より確認 ・正常時と比べ、異常音等が ないか確認 |
異常があればメーカーに 連絡する |
| 扉換気フィルタ | 扉換気 フィルタの 汚れ |
フィルタの汚れ具合を目視に より確認 |
・フィルタが汚れている場合は清掃する ・破損している場合は新品と交換する |
| LED・LCD | LCD、LEDの 表示 |
・装置のLED/LCDが点灯/表示 しているか確認 ・文字化けしていないか確認 |
異常があればメーカーに連絡する |
| 発電状況の確認 | LCDの発電表示 | LCDに表示される発電状況に 異常がないことを 目視により確認 |
異常があればメーカーに連絡する |
3.パワーコンディショナの定期点検
法定点検として、1年ごとの実施が推奨されているのが「定期点検」です。日常点検と同じ目視による点検に加え、絶縁抵抗測定なども絶縁劣化によって生じる感電や漏電の危険性を予防するため実施する必要があります。メーカーに依頼してください。
一般的に、定期点検では以下の表にある内容を確認します。
| 点検項目 | 点検事項 | 点検方法(概略) | 処置方法 |
| 周囲環境 | 周囲温度、湿度、 塵埃の有無 |
装置周囲の温度、湿度が 使用範囲内であることを 温湿度計により確認する |
故障の原因になるため、 使用範囲に入るよう 周囲環境を整える |
| 外観 | 外箱のサビ等の腐食 | 装置の外観に、サビ等の腐食が 発生していないか 目視により確認する。 |
サビ等の腐食はサビを 落としたうえで 補修用塗料で補修する |
| 内部 | 異常振動、異常音、 異臭の有無 |
正常時と比べ、大きな振動、 異常音、異臭等がないか確認する |
異常があればメーカーに 連絡する |
| 外部配線の損傷、 接続端子の緩み |
外部配線に損傷がないこと、 接続端子に緩みがないことを 目視により確認する。 |
損傷が認められた場合、 施工会社に連絡する |
|
| 絶縁劣化の有無 | 絶縁抵抗を測定する。 | (注1) | |
| 主回路電圧 | 装置のLCDとテスターにて、 回路電圧が規定値内であるか確認する。 |
異常があればメーカー に連絡する |
|
| ケーブル入線口 | 入線穴は板金で塞がれ、 かつ隙間はパテで埋まっている ことを目視により確認する。 |
異常が認められた場合、 施工会社に連絡し、 隙間を埋める |
|
| 装置内部の汚損の有無 | 装置周辺、装置床面の 塵埃有無を目視により確認する。 |
汚れている場合、 入り込んだ塵埃を取り除く |
|
| 動作チェック | 系統連系保護動作 試験等を行い、保護 回路に異常がないか。 |
系統連系保護継電器の試験を 実施し動作値を測定する。 (マスタースレーブ方式の場合、 マスター機のみ実施) |
異常があればメーカーに 連絡する |
| 扉換気ファン | 正常に回転しているか。 異常振動、異常音はないか。 |
回転していることを目視により 確認する。正常時と比べ、 異常音等がないか確認する。 |
異常があればメーカーに 連絡する |
| 扉換気フィルタ | 扉換気フィルタは 汚れていないか。 |
フィルタの汚れ具合を目視に より確認する。 |
・フィルタが汚れている 場合は清掃する。 ・破損している場合は 新品と交換する。 |
| LED・LCD | LCD、LEDの異常 表示はないか。 |
装置のLED/LCDが点灯/表示 しているか、文字化けして いないか確認する。 |
異常があればメーカーに 連絡する。 |
| 発電状況の確認 | LCDの発電表示は正常か。 | LCDに表示される発電状況に 異常がないことを目視に より確認する。 |
異常があればメーカーに 連絡する。 |
| 注1:絶縁抵抗試験は間違った方法で実施すると装置を破損する恐れがあるため、メーカーに依頼する。 | |||
日常点検と定期点検以外にも、パワーコンディショナの運転を停止して部品交換などを行う「精密点検」も行う必要があります。
4.パワーコンディショナのメンテナンス頻度
パワーコンディショナのメンテナンス頻度は、明確には規定されていません。その理由は「日本電機工業会(JEMA)・太陽光発電協会(JPEA)技術資料 JM16Z001(太陽光発電システム保守点検)」にも記されていますが、メンテナンスの頻度は以下の5項目によって大きく変わりうること、用途やサイト(場所)及びシステム所有者の責任範囲など、様々な要因があるため規定することが難しいのです。
- ●システムの種類(地上設置型発電システム、業務用、家庭用など)
- ●遠隔監視能力の程度
- ●契約規定または発電性能保証
- ●特定の機器の保守につき製造業者の推奨する実務
- ●サイト固有の考慮点
メンテナンスの頻度を決定するために考慮すべき要因をまとめた表が以下になります。
| 機器/点検作業 | P (※1) |
I (※2) |
点検頻度を決定するための要因 |
| パワーコンディショナの ランプとディスプレイから 得る通知の確認 |
〇 | 〇 | 専門技術者以外によるものを 含めて小形システムの確認に有効。 トラブルシューティングにも有効 |
| パワーコンディショナ 筐体(外観)検査 |
– | – | 低頻度又はパワーコンディショナ 製造業者指定の頻度で行う。 腐食環境をもつサイトでは頻度を高くする |
| パワーコンディショナ内部 (水、埃、げっ歯類)の確認 |
– | – | 低頻度で行う。ただし、げっ歯類の問題、 大雨、洪水及び接続電線管内で 結露が見られたサイトは除く |
| パワーコンディショナ内部 (現場接続端子の上の トルクマーク、焦げ跡の 有無)の確認 |
〇 | 〇 | トラブルシューティング又は パワーコンディショナ製造業者の 検査の一部として行う。 最初の1-2年は検査頻度が 高くなる場合がある |
| 定期保守(製造業者指定) | – | – | 指定による |
※1 測定出力が低いなどの検知された発電性能上の問題(P:performance)がトリガーになっていることを示す。
※2 地絡又は機器の故障のにような具体的な事象(I:specific incidents)がトリガーになっていることを示す。
太陽光発電を安定的に稼働させるためには、計画的なメンテナンスが必要です。
長期間安全に運用するためにも、日常点検や定期点検を通して異常の早期発見につとめていきましょう。
Products of DAIHEN

世界初!耐塩密閉構造で"エアコン・レス"を実現

750V入力で業界トップクラスの変換効率98.4%を実現

500kWパワーコンディショナに匹敵
国内トップクラスの変換効率98.4%を実現

産業用パワーコンディショナ
累計出荷台数3,000台以上のベストセラー機

産業用パワーコンディショナ
累計出荷台数3,000台以上のベストセラー機